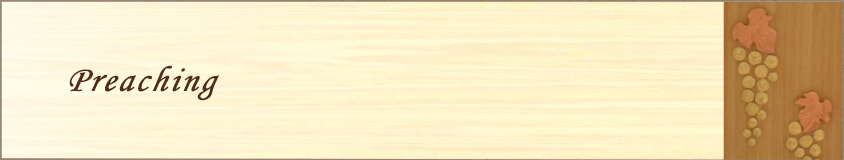年間と呼ばれる主日もいよいよ今日の日曜日で終わります。その次の日曜日は「王たるキリスト」の祭日が祝われ、今年の典礼暦が締めくくられ、新たな典礼暦年の始まりとなる待降節がスタートします。さて、年間主日の最後の頃には毎年、福音書の中の小黙示録と呼ばれる終末の有り様が語られます。確かに歴史的に見ても、西暦70年にはのちにローマ皇帝になるティトゥスによりエルサレムは陥落し、イスラエルはそれから再び流浪の民となり、第二次世界大戦後に現在のイスラエルという国家が建国されるまで国土・領土をもたない民でした。
ルカ福音書が書かれたのは、ちょうど、そのような危機が迫っていた頃です。それゆえ、イエス様が言われたことが弟子たちの心には「古きイスラエル」から「新しき神の民」への大変革として映ったことと思います。
多くのユダヤ人にとって神殿は、彼らの誇りであり、この神殿がある限りイスラエルは絶対に滅びることがないという確信を持っていました。しかし、イエス様にとっては神殿とは「神様のおられるところ」という意味であり、ご自分のことを指して言われています。「この神殿を倒してみよ、私は3日でこれを建て直す」と。また、キリスト者の共同体も「聖霊の神殿」と呼ばれます。事実、初代教会は4世紀に至るまで建物としての聖堂や神殿をもたずに宣教活動を続け、成長してきました。
エルサレムの崩壊は、ユダヤ人にとってだけでなく、キリスト者にとってもいよいよ「世の終わり」を思わせる出来事であったことと思います。しかし、イエス様のことばをよく読むとそれは「世の終わり」そのものではありません。戦争、暴動、飢饉、天災はいつの時代にもあることであると述べられているのです。大切なことは「世の終わり」ではなく、「救いの完成」の時が近づいていることを悟ることなのです。多くの悲劇的な出来事、天変地異だけでなく、人間が引き起こす悲劇が起こりますが、それらによって絶望するのではなく、「神様のご計画がこれらの悲劇によって破壊されること、失敗することはありえない」という信仰と希望と忍耐が必要とされることをイエス様は力強く述べておられます。
【祈り・わかちあいのヒント】
*この世で神を見た人はいません。しかし、「人間は死んだらどうなるか?」ということを考えたことのない人間もまたいません。あらゆる宗教は生の世界と死後の世界を結ぶ何かを語ります。キリスト教では何を教えていますか?
 未分類
未分類