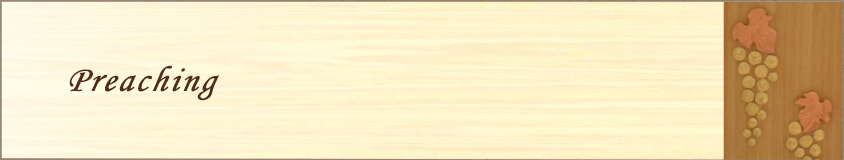
今日の福音

稲川神父の説教メモ
2026年2月8日
年間第5主日 マタイ5:13~16
「あなたがたは地の塩、世の光である」
山上の垂訓には、日本人にもよく知られている聖書のことばが度々登場しますが、今日の箇所もその一つではないでしょうか? 「あなたがたは地の塩である」とのイエス様の教えは何を私たちに示唆するものでしょうか。
まず、このことばを聞く時、幼いイエス様が台所でお料理をしているマリア様のそばに立って、見ているような場面が想像されます。「塩はとっても大切なもの、味をつけたり、人間の体に必要なもの、でも多すぎても料理全体がダメになってしまうものなのよ」とお母様であるマリア様が語っているような風景が目に浮かんできます。
私たち地球上の生物はみな、水と塩というものが不可欠なのです。多くの生物が海という塩を含む水から誕生したこと、胎児が子宮の中で育ってゆくときの羊水が海の水とほぼ同じ塩分、ミネラルのバランスであることを考えても、塩の役割は大変重要なのです。
塩の役割は、①味をつける ②清めに用いる ③呪いを意味するなど、聖書の中でもいろいろな使用例があります。味付けということを考えてみると、塩のもつおもしろい性質に対比作用というものがあります。他の味の中に塩がほんの少量入ることによって、塩の味はわからないのに、その他の味が強く感じられるということです。わかりやすい例としては、お汁粉を作る時、砂糖の他にほんの少々の塩を加えることによって、お汁粉の甘さが増すのです。
「あなたがたは地の塩」とイエス様が言われたとき、「あなたがたのことばや行ないは、あなたがた自身を目立たせるためのものであってはならない。むしろ隠れて、しかし、みんなのために、みんなを生かすという隠れた働き方こそキリスト者として必要なこと、大切なことなのだ」という意味もあったのではないでしょうか? 塩は隠し味として用いられる時にこそ、その力が大きく現れるのです。反対に塩の味がのさばると、顔をしかめられた上に、その食べ物の味さえ、壊してしまい、ひどいときにはもう食べられやしないとすべてが捨てられてしまうことさえあるのです。皆様! ご用心! 私たちが「いいこと」と思っても、隠し味としてみんなを生かしているか、それとも……
【祈り・わかちあいのヒント】
*私たちは「隠し味」としての塩の役割を果たしているでしょうか?
*塩が味を失う時とは、私たちがどのような状態の時でしょうか?
2026年2月1日
年間第4主日 マタイ5:1~12a
「悲しむ人は幸いである。その人は慰められる」
いよいよ、イエス様の教えが語られます。マタイ福音書はイエス様の教えを五つの垂訓という形でまとめており、その第1の垂訓はマタイ5~7章の「山上の垂訓」と呼ばれる有名な箇所です。その場所が「山」であったことにより、イエス様の姿が、シナイ山で旧約の神の民がどのようにして神にふさわしい民になるべきかを告げたモーセと重なります。新約時代の神の民の生きるべき道が示されるのです。
今日の福音は、山上の垂訓の冒頭を飾る「真福八端」と言われる「八つの幸い」についてです。この八つの幸いは言わば、イエス様の教えの根本的な精神を表すモットーのようなものです。その第一声「心の貧しい人々は幸いである」は、日本語では少し奇妙に聞こえるかもしれません。と言うのも「心が貧しい人だなあ!」と言えば、他の人のことを顧みる余裕もない、自分のことばかり考えている人」というニュアンスです。そこで、「聖書と典礼」の注釈にもあるように「霊において貧しい人」という訳も可能なわけです。実に、このたった1行に対し200種類もの翻訳が可能なのです。
では、イエス様が言いたかった「心の貧しい人」とは、どんなことなのでしょうか? それは、「この世のどのようなものでも解決することの出来ない、人間の苦しみを解決できるのは、神様、あなたしかいないのですということを知っており、それゆえに神様にしか頼ることが出来ない人々」という意味なのです。
「悲しむ人は幸い」とイエス様はおっしゃいますが、何故でしょうか? よく考えると「自分のことで悲しむのではなく、他の人の悲しみを自分の悲しみとして受け入れることのできる心をもった人は幸い」なのです。「いつくしみ」ということばはラテン語では「ミゼリコルディア」ですが、ミゼール(悲惨なこと、悲しみ)とコルディア(心)という二つのことばが一緒になってミゼリコルディアすなわち「いつくしみ」という意味になるのです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*なぜ「柔和な人は幸い」なのでしょうか?
*なぜ「義に飢え渇く人は幸い」なのでしょうか?
*神さまを見ることのできる「心の清さ」とはどのようなことでしょうか?
*神の子と呼ばれるために「平和を実現する」ために何をしていますか?
2026年1月25日
年間第3主日 マタイ4:12~23
今日の福音にはイエス様のガリラヤにおける宣教の開始が語られています。何故、イエス様の福音宣教はガリラヤ地方において始められる必要があったのでしょうか? 当時のユダヤ人にとって宗教的な中心地は神殿のあるエルサレム、ユダヤ地方であったのに対して、ガリラヤは異邦人の地といささか蔑まれていました。確かにガリラヤ地方には異邦人も多く住んでいました。しかし、それゆえにイエス様の福音は神の民と異邦人がともに住むガリラヤこそ、ふさわしかったのです。イエス様は、約束されたメシア、しかしアブラハムの子孫であるユダヤ人だけの救いのためではなく、万民の救い主であることをこうして明らかにされたのです。
イエス様が、ガリラヤでの宣教の開始と同時に弟子たちを呼び集められたことが、今日の福音で語られています。これにはもう一つの大切な意味があると思います。すなわち、私たちの信仰は常に共同体性を帯びているということです。「私と神様」の関係を結ぶことが信仰と考えられがちですが、「私たちと神様」の関係を深めることこそ、イエス様の信仰共同体の特色となるのです。イエス様は神様を父と呼ぶように教えられました。私たちの信仰は最初から共同体との関わりなしには生まれないのです。ちょうど私たちの人間としての誕生が父と母という共同体から生まれたように。
私たちの信仰の基本は、(1)神様と愛と命の絆で結ばれるために今日も祈ること。(2)キリストを師として、信仰と与えられた人生をよりよく生きるために学び続けること。(3)私を支えてくれている仲間に感謝し、私も仲間のために何をなすべきかを問い続けること、そして行うこと。祈りなしの信仰は直ちに暗闇に沈んでしまいます。学びなしの信仰は自分の作り出す誤った固定観念によって生きた信仰を失わせます。奉仕のない信仰は不平と不満だけをやたらに人にぶつけるだけの愚か者にしてしまいます。ペトロたちはガリラヤ湖の漁師でした。陸地のように安定した場所、自分の才覚で生活の糧を稼ぎ出すというよりは、自然という、人間の力ではどうすることも出来ないものを相手にする、不安定で先の見えない職業に従事していました。だからこそ、決断と行動が早く、自分独りの力よりも仲間とともに力をあわせ、また神様に信頼をもつことなしには日々の生活が成り立たない人々でした。「すぐに網を捨て」、「すぐに舟を捨て」イエス様についていった4人はやがて弟子たちの中でも中心メンバーとなってゆきます。「また今度にします。いつかはそうなりたいと思います」と言い訳しがちな私たちですが、今日、新たな気持ちでもう一度始めたいと思います。
【祈り・わかちあいのヒント】
*「すぐに」と「ともに」は私たちの信仰の特徴です。あなたは「今」、「誰とともに」この信仰の道を歩んでいますか?
2026年1月18日
年間第2主日 ヨハネ1:29~34
先週の日曜日に祝った主の洗礼から年間という季節が始まります。それに続く年間第2主日にはヨハネ福音書の記事が朗読されます。洗礼者ヨハネが述べた「神の小羊」という表現は、今日もミサの中で私たちが用いているイエス様の称号です。「神の小羊」ほど、イエス様の使命を端的に表している表現はありません。「小羊」と言えば、イスラエルの人々にとっては「過越しの食事」を連想させるものでした。あのエジプトからの脱出の時、モーゼはイスラエルの人々に命じました。「傷のない一歳の小羊をほふりなさい。その血を各家の入口の鴨居(横木)と柱(縦木)に塗りなさい。その血を見て、主の使いはイスラエルの家と知るであろう。そして、主の下す災いは過ぎ越すであろう」。過越しの食事はイスラエルの人々にとって、神の救いのわざにあずかるしるしとなりました。彼らは年に1度の過越祭の食事にエルサレムであずかることにより、自分たちが神の民であることを確認しあったのです。
このような宗教的な背景がある中で、洗礼者ヨハネがイエス様を神の小羊と言った時、2人の弟子(ヨハネとアンドレア)は、「先生が『神の小羊』と言われたこの人にはきっと何かがある!」と思い、その後をついて行ったのです(ヨハネ1:35~42)。洗礼者ヨハネは「神の小羊」という表現をもって、イエス様が十字架(横木と縦木の組み合わされた形)の上で、自らの血を流し、自らをいけにえとして捧げ、それによって世の罪を贖い、世を救われるお方であることを最初から宣言しているのです。だから、この方こそ、「神の子」であると証しするのです。「神の小羊」が今日もミサの中で繰り返し使われるのには、それだけ大きな意味があるのです。
私たちはイエス様をどのようなお方であると表現していますか?
「私にとってイエス様とは、○○○○○である」という自分らしい信仰表現を持つことのできる人は幸いだと思います。イエス様ご自身もいろいろな表現でご自分のことを言い表しておられます。「私は天から下ったパンである」「私は世の光、道、真理、命である」「私はぶどうの木」「私は一粒の麦」などなど。これらの意味を深く受けとめ、味わい、私たちの心の中にいつもイエス様の姿があらわれているように生きてゆきたいと思います。
【祈り・わかちあいのヒント】
*あなたはイエス様をどのようなお方であると表現できますか?
*あなたにとってイエス様を語る時のキーワードは何ですか?
2026年1月11日
主の洗礼 マタイ3:13~17
私たちの信仰生活の出発点は洗礼です。もちろん洗礼の以前にも神様を信じ、祈りを捧げ、キリストの福音を受け入れてはいますが、洗礼は自分一人の信仰ではなく、キリストの共同体としての信仰に入るという意味では、正式、公式、決定的、そして超自然的な恵みなのです。
イエス様も公の宣教生活のはじめを洗礼に結び付けています。ヨルダン川の洗礼者ヨハネのところにやって来られた時、洗礼者ヨハネは、驚きました。「わたしこそ、あなたから洗礼を受けるべきなのに」と。洗礼者ヨハネは「私の後から来る方は偉大な方で、私はその方の履物のひもをとく値打ちもない」と公言していたくらいですから。しかし、イエス様は一言、「こうすることが私たちにはふさわしいことです」とお答えになりました。すると、さすがに洗礼者ヨハネです。イエス様の言われる意味をたちどころに悟りました。
- イエス様は神のみ子です。その方が人間の仲間となるために人間の姿でこの世に来られたのは、徹底的に、完全に人間、人の子として生きることを通して、神の子となる道を人間に示すためでした。
- イエス様が水の洗礼を受けられることにより、ただの清めや洗い以上の意味が洗礼に加わりました。すなわち、イエス様の受けるべき洗礼は、十字架の苦難・死そして復活を意味していました(マルコ10:38)。こうして、イエス様が水の洗礼に新約時代の意味を加えて下さったのです。
- 水は聖書の中で様々な意味に用いられています。ある時は生命のシンボルとして、そしてある時は、清め、滅び、死のシンボルとして。イエス様は、「私は生ける水を与える」(ヨハネ4:10)と言われています。「私が与える水は、その人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る」と語っておられます。水はイエス様の与える聖霊のシンボルとなります。
- やがて、イエス様は十字架上において、その開かれたわき腹から「血と水」を流されます(ヨハネ19:34~35)。その瞬間に弟子のヨハネは新しいアダムであるキリストのわき腹から、新約のエヴァ、キリストの伴侶であり花嫁である教会が誕生したことを悟るのです。洗礼者ヨハネが「水の洗礼」の意味を瞬時に十字架の死と復活につながるものと理解したように、弟子のヨハネもキリストの死が教会を誕生させるための道であったことを悟るのです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*洗礼は古い自分に死に、新たに生まれることが求められています。
あなたは何を退け、何を受け入れて、今日を歩もうとしていますか?
*フランシスコ教皇は「パートタイマーの信者になってはいけない」と言っています。都合のよい時だけでなく、いつも変わらぬ心でいるためには?
