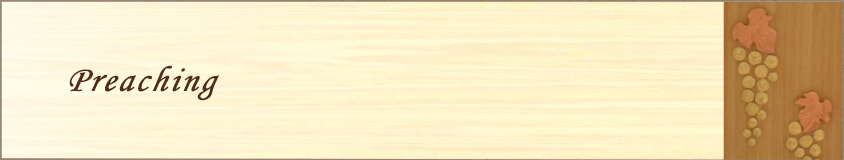
今日の福音

稲川神父の説教メモ
2025年7月13日
年間第15主日 ルカ10:25~37
ルカ福音書には、芸術家の福音書という別名があります。ルカ福音書の描くキリストの出来事、また様々な教えは、絵画や彫刻、音楽、演劇にたくさんのヒントを与えてきたからです。さて、ルカ福音書は、「たとえ話」の福音書とも言えると思います。イエス様のたとえ話といえばかならず思い出されるものの多くが、ルカ福音書に記されています。今日はその代表例である「よきサマリア人のたとえ」です。
このたとえ話の導入は、ある律法の専門家の質問です。「永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいのでしょうか?」イエス様はまずそれに直接答えようとはせず、「律法には何と書いてあるか? あなたはそれをどう読んでいるか?」とお尋ねになります。すると、その人は「神と隣人を愛すること」と答えます。イエス様はそれを正しい答えと認め、それを行なうように諭されます。すなわちイエス様の答えは、知っていることでとどまらず、行なうこと、どう理解し、実際の生き方にどう結びつけているかが大切であると強調しておられます。このことはキリスト者にとって大切なことを意味しています。信仰を知識と同一視しがちな人々が多いからです。仏教でも「慈悲」を説き、儒教でも「仁」を説きます。教えの内容としては、つまり知識のレベルではキリストの説く「愛」と大きな差はありません。ただキリスト教の特徴は、人生を達観し、悟りを開くためや政(まつりごと)を行なう心構えを説くのではなく、私たち平凡な一人ひとりの人間に「行なうこと」を促がすところにあるのです。
このたとえ話は「自分がどう救われるか?」について尋ねてきた人に、「あなたは誰の救い手となるか?」と切り返してきます。私たちの信仰は「自分の救いのため」という発想から見直すことを要求されます。自分のことを忘れて「誰かのために一生懸命」な時こそ、もっとも自分自身が生き生きしている時なのです。反対に、自分の健康、自分の運不運、自分の思いや都合にとらわれている時は「いつもどこかに不安やいきづまり、閉塞感を感じている」のではないでしょうか? それゆえに隣人が必要なのです。隣人は私をわずらわせるめんどうな人ではなく、私がもっといきいきと生きるために必要なチャンスを与えてくれている人たちなのです。
今の時代は権利を主張する人たちが大勢います。しかし、キリストは「まず、神の国とその義を求めよ、そうすればすべての必要なことはおのずから与えられる」と教えておられます。自分のことばかりしか、目に入らない、関心がないという「自分中毒」ということに陥ってしまっている人間が多くなってはいませんでしょうか?
【祈り・わかちあいのヒント】
*あなたは誰の友人、隣人となっていますか?
2025年7月6日
年間第14主日 ルカ10:1~12, 17~20
今日の福音朗読はルカ10章です。ここには72人の弟子の派遣が述べられています。面白いことに、このすぐ前の9章にも12人の派遣が述べられています。これはルカ福音書の特徴です。他のマタイやマルコには12人の弟子たち(使徒たち)の派遣が教育実習のように述べられていますが、ルカでは、12人に続いて72人の弟子たちの派遣がすぐ後に繰り返し述べられているのです。
ここには、ルカ福音書が異邦人キリスト者のために書かれたものであるという性格が表われているのかもしれません。ルカ福音書が記された時代には、キリストの教えがイスラエルの人々に限定されるものではないことが、すでにいろいろな教会共同体の誕生により、実感できるものとなっていたのです。72という数字は12×6=72すなわち新しい神の民×月~土(6日間)の努力の上に神様が祝福を与え、日曜日に集うということと考えることができます。こうして、新しい神の民に加わる人々が全世界規模で広がって行くために、「働き手」となることが呼びかけられているのです。
12人の場合も、72人の場合も、共通しているのは「何も持たずに行きなさい」という点です。これは、宣教とはどこか遠い場所へ出かけて行くことだけではなく、むしろ私たちの日常生活の場こそ、宣教の場であることを示していると思います。私たちは信徒で司祭やシスターのように外国に宣教には行けない、と宣教を限定して考えてしまいがちな私たちに、福音書の記事は、生活=宣教ということを教えています。ルカは特に使徒行録の中では、宣教=証しということばを使います。宣教と言うとことばや理論的な説明と理解しがちですが、ルカはもっと「行ない」を重視していると言えます。
「子どもの使徒職」ということばを聞いたことがありますか? もっとも身近な人々への宣教こそ、私たちキリスト者の優先課題です。子どもに信仰を伝えることは両親の第1の義務になります。その子どもにも使徒職があると、ある人々は言います。子どもの使徒職とは「なぜ」と問い掛けることなのです。この子どもたちの「なぜ」ということにちゃんと向かい合うことが大切なのです。「育児とは育自である」と言った人もあるくらい、子どもを育てるには親自身もともに学ぶことが必要なのです。幼い子どもになぜということを理論として説明しても、子どもはわかりません。その説明された事柄も覚えてはいないこともしばしばです。でもその子も自分に向かい合ってくれた実感は覚えているのです。その思い出が大切なのです。親の顔の中に神様の顔が見えるのです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*神様があなたに期待している「使徒職」は何でしょうか?
2025年6月22日
キリストの聖体 ルカ9:11b~17
聖霊降臨の主日の後に、神の救いのみわざ全体を統合するテーマとして「三位一体」「キリストの聖体」を祝う主日が続きます。今日の福音の朗読箇所は、5000人にパンを与える奇跡のエピソードですが、ルカ9章16節のイエス様のことばと行いは、新約聖書全体では10回も記述されているものです。そしてルカ福音書では特に次の点が特徴となっています。【祈り・わかちあいのヒント】
- 神の国について語り、人々をいやすイエス様(11節)
ご自分を求めるすべての人々を迎え、受け入れるイエス様の優しい愛、イエス様における神の国の現存、イエス様によるいやしを、一連のものとして考えています。すなわち、「神の国」とは「神の愛と恵みの場」であり「イエス様自身」こそ、その見える姿であり、それを「聖体」として、すなわちあらゆる時代のキリスト者へ与えようとするイエス様の姿が描かれています。あらゆる時代のキリスト者が「イエス様のことばと行い」を繰り返すとき、イエス様はその中におられるのです。イエス様とともにいる豊かさは12のかごに用意されているように、さらに多くの人々のために与えられるものなのです。- 弟子たちのことば、群衆への心遣い(12節)
「もはや日が傾きかけた」ので、弟子たちは集まった人々の食事や「宿」のことを心配してイエス様に語りかけました(ルカ24章のエマオの弟子たちに現れたイエス様を連想させることばです)。ここは人里離れたところ、イスラエルの先祖たちが歩んだ荒野の旅の間、天からのパンがイスラエルの人々の命を支えたように、イエス様はご自身を求め、信じて従ってきた人々に、天からのパン=ご自身を与えようとするのです。- イエス様のチャレンジと弟子たちのこたえ(13節)
イエス様は弟子たちの提案に対して不思議なことを命じられます。すなわち、「あなたたちが食べるものを与えなさい」と。「5つのパンと2匹の魚しか、手元にありません」という弟子たちのこたえは正直であり、また現実的であり、人間の力ではこのチャレンジにこたえようもないことが感じられます。イエス様はただ一人でこのことを解決しようとはなさらず、弟子たちをご自分のなさろうとする救いのわざに参加させようとしているのです。弟子たちは、イエス様に命じられたように人々を50人、100人の組にしてすわらせました。イエス様が祝福して裂かれたパンを、人々一人ひとりの手に渡してゆきました。パンは力の泉(詩104:14~15)、神のことば(アモス8:11)、神の恵み全体のしるし(ルカ11:3)、イエス様ご自身(ヨハネ6:35)のシンボル。
*今、私たちの手元にある5つのパンと2匹の魚は何でしょうか?
2025年6月15日
三位一体の主日 ヨハネ16:12~16
四旬節から復活祭、そして聖霊降臨という大きな典礼の季節を締め括るのは、今週と来週の2回の主日です。そのテーマは「三位一体」と「キリストの聖体」です。実は、この2つのテーマは救いの歴史全体をあらわすキーワードなのです。したがって、別々の主日ではなく、三位一体と聖体には深いつながりがあるのです。
この日曜日のテーマである「三位一体」は実はミサとの関連があります。初代教会の人々は「父と子と聖霊」をすでに実感し、信仰を持っていましたが、それが理論化され、体系化されてゆくには時間がかかりました。その歴史のあいだには、キリストの神性を疑問視したり、反対にキリストの人性を疑問視したり、聖霊だけを切り離して強調する人々があらわれたりし、15世紀のフィレンツェ公会議においてようやく神学的な理論が定まりました。三位一体の主日がカトリック教会全体で祝われるようになったのは10世紀ごろからです。そして、三位一体の信仰が教会の教えの根本であることを明確にするために、ミサを「十字架のしるしと三位一体への信仰告白のことば」で始めるという習慣が、ここからスタートしたのです。私たちキリスト者にとってはごく日常的な動作ですが、キリスト者ではない人々にとっては、この動作をしているキリスト者を見る時に新鮮な驚きを感じるようです。
さて、三位一体の神について論理的な叙述はおよそ不可能です。むしろ、三位一体の特徴を受け止めることに心を向けてみましょう。神さまの本性は「愛」なるお方ですから、三位一体を説明するには「愛」を手がかりにすることがふさわしいと思います。愛は一人では成り立ちません。また自己愛は不完全な愛ですから、愛には対象が必要です。父と呼ばれる存在と、その父の愛を完全に受け入れる子という存在の間に共有される愛こそ、聖霊と呼ばれるお方です。父と子の両者の間だけでは愛は完結しません。愛は、両者が心をあわせて共通の方向に向かう時に完全なものとなります。父と子より出でて神様の愛の対象となる存在、すなわち私たち人間に神様の愛が遣って来られるのです。それが人となった神の子、イエス様であり、イエス様と御父の持つ完全な愛の心を私たちに与えることのために、十字架という完全な従順、祈り、信仰の姿が示されるのです。そして、イエス様の後に従って十字架の道を歩ませるよう力づけ、イエス様のことを絶えず思い起こさせるのが聖霊の働きです。聖霊は私たちの中に留まり、私たちを父と子の愛の交わりの中に引き上げてゆくお方なのです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*祈りのはじめに「父と子と聖霊のみ名によって」と十字のしるしをするのはカトリックだけで、プロテスタントでは行なっていないのは何故でしょう?
2025年6月1日
主の昇天 ルカ24:46~53
復活祭から40日後、主の昇天の祝日を祝います(日本では復活節第7主日に昇天を祝います。)私たちが親しんでいる昇天のイメージは、ルカ福音書が記すように手を上げて弟子たちを祝福しながら天に昇られる姿です。今年の主の昇天においてはルカ福音書の最後の部分が朗読されます。この福音書において強調されているのは、イエスの復活と昇天の神秘が、教会の宣教活動の開始となる聖霊降臨と深いつながりがあるということに直接ふれていることです。
- イエスの復活と昇天が弟子たちを使徒へと変える⇒イエスの与えた使命が弟子たちを変える⇒イエスの使命を受け継ぐ弟子たちが使徒たちへと成長し、全世界へ派遣されるのです。その第一歩としてイエスは約束されたもの(聖霊)を待ちなさいと命じるのです。使徒たちの宣教の第一歩が「祈りながら聖霊を待つこと」であったことは印象的です。
- ルカ福音書・使徒行録において、宣教は「証し・証人となること」という表現が多用されています。証人とは自分の考え出した理論を語ることではなく、自分の体験したことを語ることです。これは今日の私たちの宣教についても大切なことです。
- ルカ福音書の語るイエスの昇天は、あたかもイエスがこの地上から離れ去ってゆき、もう目には見えない遠い、高い天空に行ってしまったように思えるかもしれません。しかし、「天」(ヘブライ語でハッシャマイーム)は、「高い」「遠い」という意味合いだけでなく、私たちが地上のどこにいても必ず「私たち」とともにあるものという意味合いがあることを忘れてはなりません。
- オリーブ山でイエスを見送った弟子たちは神殿に集まり、絶えず神を賛美していたとルカは記しています。ルカ福音書は、神殿の祭司ザカリアに天使ガブリエルが洗礼者ヨハネの誕生を告げる物語から始まり、弟子たちが神殿で神を賛美する姿で終わっているのです。
- 弟子たちのなすべきことは直ちに行動を開始することではなく、祈り、賛美し、そしてイエス様が送られる聖霊を待つことでした。祈りなしには宣教は不可能です。イエス様ご自身の生涯もその宣教活動においても、祈りすなわち御父との対話、交わりがあったからこそ、「私の思いのままではなく、あなたのみ旨が実現しますように」ということを行なうことが出来たのです。この姿勢は私たちの今日の教会活動についても同じことが言えるのです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*イエス様の昇天は復活の出現があらゆる時代に続くことを暗示しているのではないでしょうか? あなたはともにおられるイエス様と話していますか?
