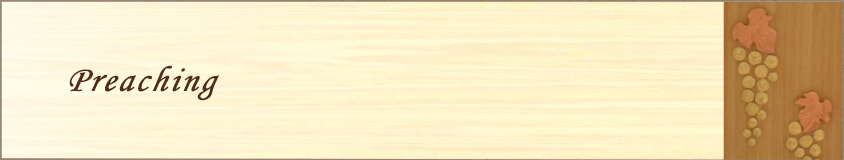今週もルカ18章に記されている祈りに関するたとえ話で、その2つ目のものです。真の祈りとはどのようなものか、祈りがへりくだる心で神のあわれみに生かされているものでなければならないということが、このたとえ話を通して示されています。二人の祈りはあらゆる点で対照的です。ファリサイ人にとって神殿に来ることは誇りであり、歓びです。彼は立ち上がって祈ります。彼の祈りは一見すると感謝のように見えますが、彼が感謝の理由として述べていることは「神様がしてくださったこと」ではなく「自分が行ったこと」です。彼の祈りのことばには「私が」「私が」と自分しかありません。さらに決定的なのは兄弟(他者ではあっても決して他人ではない人間)に対するいたわりや思いやりがありません。律法社会の落伍者、弱い立場にある人々の生活、生きることの難しさ、傷ついた心に対する感受性が欠けています。彼は自分自身もそのような弱さを持っていること、罪の現実に自分も取り巻かれ、おびやかされていることを忘れてしまっています。
イエス様は祈りの3つの条件(マタイ6:5~15)の中に、兄弟に対する愛と赦しを要求しています。祈る時、兄弟に対する愛が欠けていれば、神様からも退けられてしまうのです。弱さの中にいる他の人々をあざけることなく、その人々の苦しさ、悲しさを自分の身に負うことこそ、神様の求めるものなのです。
もう一人の人、徴税人の祈りは何故、聞き入れられたのでしょうか? 徴税人の祈りは「神よ、罪人である私をあわれんで下さい」というただ一言でした。彼はファリサイ人のように自分を誇るものを何一つ持たず、堂々と前に進み出ることも、まっすぐに天を見つめることも出来なかったのです。彼に出来ることは、自分の罪についてあれこれと弁解することではなく、みじめな自分、言い訳できないほど汚れている自分の姿を神様の前に投げ出すことだけでした。この罪に汚れ、不安、苦しみ、孤独にさいなまれ傷ついて、苦しんでいる自分を救えるのは、「神様、あなただけです」と彼は表明しているのです。
この一言の祈りはイエス様の示す祈りの3つの条件(マタイ6:5~15)を満たしているのです。すなわち、彼は見せびらかすためでなく(第1の条件)、くどくどと言うことなく(第2の条件)、神への信頼にすべてを委ね(主の祈り)、兄弟に対して犯した罪に対する痛悔の心(第3の条件)を表わしています。私たちの発言、意見、考え方は、この徴税人のようにへりくだったものでしょうか? それともファリサイ人のように「私が、私が」という傾向が見られるでしょうか?
【祈り・わかちあいのヒント】
*私たちのよく祈ること、あまり祈らないことはどんなことでしょうか?
 未分類
未分類