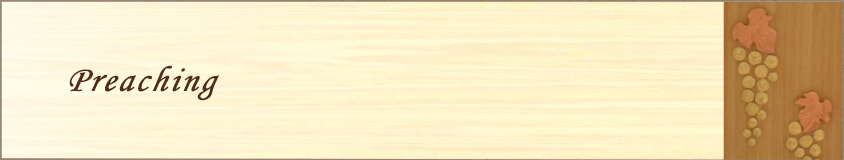今日の朗読のテーマは、神様から招かれた人のとるべき態度です。それは「謙遜」という一語に要約されますが、聖書の言う「謙遜」とは単なる謙譲の徳ではなく、人間全体に関わる根源的なもので、「神の前における人間自身の身の持しかた」だと言われています。(高橋重幸師『主日の聖書』より)
イエス様は食事の席でいろいろお話をする場面が、福音書の中に度々登場します。当時のイスラエルの人々の習慣について、まずお話ししてみますと、当時のイスラエルの人々は普段の日は1日に2食であったようです。日本でもおやつということばに残っているように、八つ時(今の午後2時ごろ)に朝食と夕食の合間に食べ物を摂っている様子を興味深く記している『枕草子』の一節を読んだことがあります。イスラエルでは、安息日には3食摂ることになっていました。特に会堂での礼拝が終わってからの昼食は盛大な食事でした。これは神様が天地創造から7日目を安息日とされたことを記念し、神様とともに生きることの豊かさを表わすものでした。したがっていろいろな人々が招待され、招待されることは、兄弟姉妹、家族同様、親しい友人であることを表わすものでした。
イエス様はこのような食事の席に招待され、そこで様々な教えを説かれました。徴税人であったレビ(マタイ)の家に招待された時、ファリサイ人は弟子たちに文句を言っています。「あなたたちの先生は罪人たちとともに食事をしている」と。するとイエス様は答えられます。「医者を必要とするのは病人である、それと同じく私が来たのは正しい人を救うためではなく罪人を救うためである」と。イエス様は招いてくれる人が誰であるかにはこだわりません。今日はファリサイ派の議員というかなり身分の高い人物の招待でした。このような人の招待ですから、招待されてやってくる人々も同じように名士たちなのでしょう。イエス様はその人々が上席を選ぶ様子を見ていて語り始められました。「宴会や食事の席に招かれたら上席を選んではならない」と。
これは単なる謙譲の美徳の勧めではありません。日本でも上席を譲り合ってなかなか席につかないでいる様子をみることがあります。ああいうところだとお互い席を譲り合ってなかなか着席しないのに、電車やバスの中ではお年寄りが来ようが、赤ちゃんを連れた人が来ようが席を譲らないのは何故でしょうか? イエス様の言いたかったことは謙譲の美徳の勧めではなく、私たち人間はいつも神様の前に立っていることを忘れてはならないということではないでしょうか? 他人の目はあれだけ気にするのに神様のまなざしはどうして気にしないのでしょうか? 神様が喜ぶのは「周りの人々に対する思いやりの心を持っていること」ではないでしょうか? ところでどうして聖堂の一番前の席はいつもなかなか座る人がいないのでしょうか? 聖堂内のどの席も神様から見れば同じなのに。
【祈り・わかちあいのヒント】
*あなたは神様に会える時、どの席に座りたいですか?
 未分類
未分類