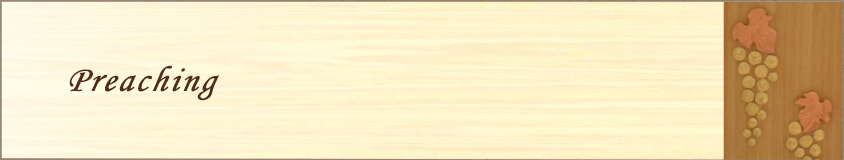今日の日曜日のミサにおける朗読箇所には、一貫したテーマが感じられます。それは「神を待ち望むこと」です。第1朗読では知恵の書が朗読され、「順境も逆境も心を合わせて受け止める」ことが神の民の生き方であることが語られ、あの過ぎ越しの出来事を待ち望んだ先祖たちと同じく、その子孫であるイスラエルの人々にとっても「神を待ち望むこと」が信仰における大切なキーワードであると宣言されています。第2朗読でも「あなたの生まれた国を離れなさい」と命じられたアブラハムが「行く先も知らずに出発したこと」が語られています。天のふるさとを目指して旅することはアブラハム以来、すべての信仰者の原点となりました。
信仰においては、「生まれた国」すなわちこの地上の社会的価値観から「天のふるさと」すなわち神様の価値観への方向転換が求められるのです。私たちは幸せで安定した生活をしているとそれがすべてと思い込み勝ちです。でも、この地上の生活では安定も幸せもつかの間のものに過ぎないことをいつか知ることになります。私たちは、生まれ、育ち、自分の望む生き方で歩んでいるように思いますが、これらのことはすべて「誰かによって支えられているからこそ可能なこと」なのです。それらのものは、病気になったり、仕事が不調になったり、家族や仲間とうまく行かなくなれば、いともたやすく失われてしまうものなのです。イエス様のたとえ話は、「今」「目に見えているもの」は決して永遠ではないこと、もし恵まれている状態ならば、その恵まれていることに感謝の気持ちを忘れてはならず、またその恵みを自分だけに用いることは誤りであること、反対に、もし恵まれた状態でなくても、絶望したり人々や神様を恨んだりすることはなく、その試練にあってこそ信仰が鍛えられるものであることを述べています。
「順境にあっても逆境にあっても」という第1朗読のことばは、現在では「結婚式の誓いのことば」の一節に使われるほど有名になりましたが、本来は信仰者の姿勢・覚悟・戒めを述べる聖書のことばなのです。「順境」、すなわち健康にも恵まれ、仕事も順調、家族や友人とも仲がよい順風万帆な時だけ信仰するというのでは、本来の信仰ではありません。全くの逆風、嵐、試練の時にあっても信頼・祈り・努力・希望を失わない姿勢・生き方が、信仰者には求められていることをイエス様は強調されています。私たちが生きるために必要なものがいろいろあります。食べるもの、着るもの、住むところ、お金、仕事も……。しかし、それだけではありません。イエス様は言われます。「あなたがたの富のあるところにあなたがたの心もある」と。私たちの心が何に向けられているか? 誰に向けられているか? 今、私たちの心に関心が向いているものが本当に私たちに真の幸せをもたらすものか、もう一度、見つめ直してみなければなりません。
【祈り・わかちあいのヒント】
*多くを任された者は、多く要求されるのです……。
 未分類
未分類