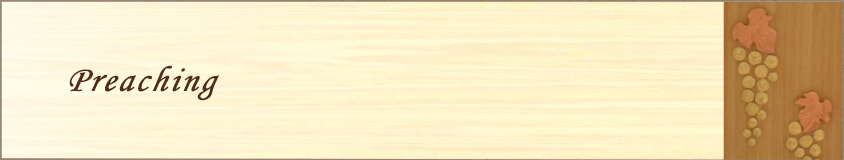降誕節が終わってから四旬節が始まるまでの間、主の洗礼の祝日から年間と呼ばれる日曜日が数回続きます。年間と呼ばれる主日には、イエス様の公生活、すなわち宣教の活動の一場面が朗読されてゆきます。さて、今日の福音は、C年ですがルカ福音書ではなくヨハネ福音書から朗読が行われます。それはヨハネ福音書のみが記しているカナの婚礼での出来事です。ヨハネ福音書の1~12章は、「しるしの書」と呼ばれるように、イエス様の「7つのしるし物語」を中心として、イエス様が誰であるか、またそのイエス様を信じることとはどのようなことであるか、ということを意味深く展開してゆきます。
カナの婚礼には、イエス様を知るためのいろいろな手がかりやしるしが残されています。
「3日目に」とは?(3日目に起こった大いなる出来事とは?)
「イエスの母がそこにいた」とは?(イエスの母はあの十字架のもとにもいたのでは?)
「婚礼」とは?(婚礼と男女の出会い、愛による生活、イエス様は神様と人間を出会わせ、愛によって結びつけるためにやって来られたのでは?)
「婦人よ」という呼びかけは?(あの十字架のもとでくりかえされることばでは?)
「この人の言う通り、何でもして下さい」という母の言葉は?(私たちに求められている信仰の姿勢では?)
しもべたちの行ったことは?(水を汲むという単純な労働の繰り返しだが?)
「あなたは良いぶどう酒を今まで取って置かれました」という世話役の驚き? (最初はこんなことと思うことがやがて……神様らしいやり方では?)
ヨハネは、私たちがイエス様と今日出会うために「確かな」手がかり=しるしを残してくれているのです。それゆえ、そのしるしを手がかりにして生きているイエス様を探すことこそ、私たち信仰者に必要な態度、心構えなのです。
ヨハネにとって信仰とは「受動的なもの」ではなく、しもべたちのように実際に汗を流し、時間と手間をかけてイエス様とともに働く中で「やがて気がつくこと」なのです。「このお方だ! これをなさったのは!」と。イエス様は人間の努力、協力を求めています。私たち人間だけの力では、水=この現実の世界をブドウ酒=人々を喜ばせる世界には出来ません。しもべたちの努力の上にご自分の力によって祝福される時、水という単純なものがブドウ酒という人々を喜ばせるものに変えられたのです。私たちはまだ水を汲んでいません。あるいは水を汲むことに飽きてしまっているのでは……
【祈り・わかちあいのヒント】
*6つの石のかめとは何のことでしょうか?(私たちの働くべき日は何日?)
 未分類
未分類