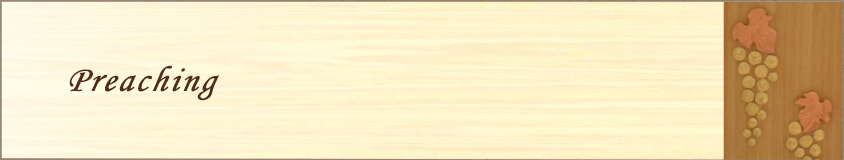今年は典礼暦年がB年にあたりますため、年間第17主日から年間第21主日までの間、福音は、ヨハネ福音書の6章が5つの主日にわたって朗読されます。イエス様はナザレ訪問の後から、ご自分の神秘である「神の子メシア」であることを少しずつ語り始めます。マルコ福音書の6章から8章にかけてパンを増やす奇跡が2度語られ、さらにパン種、パンの残りなど18回もパンに関する記述が出てきます。聖書学者がマルコ6~8章を「パンの段落」と名づけるほどです。さて、典礼暦年ではこのマルコが重要視しているテーマを深めるために、「ヨハネの聖体論」とも呼ばれるヨハネ6章が5週にわたって朗読されます。それほどヨハネの6章は豊かで、深遠な内容をもっています。
四福音書が必ず記すイエス様の大きな奇跡、しるしのエピソードですが、ヨハネ福音書は、他の福音書よりさらに詳細なところに目を注いでいます。まずこの大きなしるしがイエス様のイニシアチブによって行なわれていることです。他の福音書では弟子たちが群衆の心配をしはじめて、「もう3日も一緒です。そろそろ解散させてはどうでしょうか? そうすればめいめい、村や町に行ってパンを手にすることが出来るでしょう」とイエス様に話しかけていますが、ヨハネではイエス様ご自身が弟子たちに問いかけることから始まっています。「この人たちに食べさせるには、どこでパンを買ってくればよいだろうか」と。弟子たちはイエス様に問いかけられて、何とかしなくてはと知恵をしぼります。
フィリポは、自分たちの貯えを全部持ち出しても足りないでしょうと途方にくれます。アンデレはとにかく今、パンがどれほどあるのか、人々の間を探し回ります。ようやく5つの大麦のパンと2匹の魚をもっている少年と出会い、イエス様のところに連れて行きます。この徒労にも見える弟子たちの努力や素直に大麦のパンを差し出す姿こそ、イエス様の待っておられたことではないでしょうか? 人間の力だけでは解決できません。しかし、神様は人間の努力を「無力、無意味なもの」とはなさらず、彼らの努力の上にこそ、恵みを注がれたのです。この少年はどうして、5つの大麦のパン(貧しい庶民のシンボル)をもっていたのでしょうか? このパンの背後に、このパンを持たせてイエス様の話を聞きに行かせた少年の母親、家族の姿が思い浮かんで来ます。イエス様はそのような小さな、しかし行き届いた心遣いを喜んで受け入れ、祝福し、分かち与えるのです。みんなが家族のように思えば、この世は変わるのです!
【祈り・わかちあいのヒント】
*私たちがイエス様に差し出すことのできるものはなんでしょうか?
 未分類
未分類