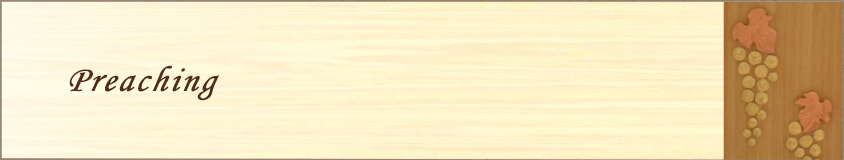「あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい」
聖霊降臨の主日の後、三位一体の主日と聖体の主日という神学的なテーマをもった日曜日が祝われます。三位一体ということはすでに聖書にそのことが現れていますが、カトリック教会の神学の中でも大変難しいテーマであり、15世紀のフィレンツェ公会議においてようやく神学的な理論が定まったという経緯があります。10世紀頃、三位一体の主日が全世界の教会で祝うべき祝日となった頃から、ミサを三位のみ名を唱えながら十字架のしるしをして始めるという形が広まりました。三位一体を聖霊降臨の後に祝うのは、三位の神が救いの歴史の始まりであり、また完成の到達点であることを示しています。
すでに古代の教父オリゲネスという神学者は救いの歴史を「父から父へ」という一言で表しています。わたしたちは、この三位一体を理論として学ぶことや人間の理性で理解することよりも、この三位一体の神様の愛に包まれて生きることを目指しているのです。
今日の福音書はマタイ福音書の最後の部分です。そこには弟子たちを全世界に派遣するキリストのことばが語られています。その特徴は、①すべての民をわたしの弟子にしなさいということ、②父と子と聖霊のみ名による洗礼を授けること、③世の終わりまでいつもあなたがたとともにいるということに要約されます。
この箇所によれば、宣教とはイエス様と人々が「師と弟子」の関係となること、すなわち、イエス様に学びながら、イエス様と行動をともにすること(=世の終わりまでいつもあなたがたとともにいる)を意味しています。イエス様の弟子になることは、父と子と聖霊のみ名による洗礼を受けることによって始まります。父と子は一つであり、すべてのことを与え合っておられます。それゆえ、わたしたちを父と子の交わりに招き、わたしたちを父と子の親しい関係に導くために、聖霊がわたしたちのところに父と子から送られてくるのです。この聖霊の導きを通して、キリストに出会い、従い、学び、歩んでゆこうとする人々が弟子たちと呼ばれるのです。興味深いのは、この箇所において、イエス様からこのことばを聞いている弟子たちの中に、「疑う者」もいたと記されていることです。理論として考えれば疑いは尽きることはありません。理論ではなくとりあえず歩み出すことによってわたしたちの信仰は始まるのです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*イエス・キリストの弟子であることがわたしたちの日々の生活の中でどのように実行されているでしょうか? わたしたちの祈り、ことば、行いは?
 未分類
未分類