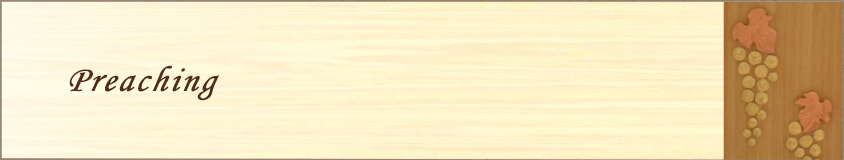「真理とは何か?」
いよいよ年間主日も最後です。典礼暦B年も王たるキリストの主日を祝って締めくくられます。さて、福音朗読の箇所はヨハネ18章です。ローマ人でありその当時の全世界といっても過言ではないほどの領土を持つローマ帝国の総督としてユダヤの地を治めていた人物、すなわちピラトとイエス様の姿が語られます。ローマ総督はユダヤの王よりも権限があり、イエス様だけでなくイスラエルという民族、ユダヤという国の生命を握っていた人物です。イスラエルの民衆はイエス様をメシア王として理解していました。もしイエス様がイスラエルの解放のため武器をとってローマ帝国と戦えと言えば、民衆は喜んで従ったことでしょう。しかし、かろうじてローマ帝国に生存を許されているユダヤ国家の指導者たちにとっては、大変危機を感じさせることでした。当時の政治的指導者を恐れず、宗教的な指導者のことばよりもナザレのイエスのことばを喜んで聞く民衆の姿を見るにつけ、彼らは「この人はやがてユダヤの新しい王になると言い出すだろう」「もし、本人がそう言わなくても民衆たちがナザレのイエスを担ぎ上げて暴動を起こすかもしれない」「そうなってからでは遅い、多くの人々が犠牲になるよりも一人の人の犠牲ですむならば」、と思ったのです。
ユダヤ人の大祭司、長老たちはついにイエス様をとらえ、なきものにしようと裁判に掛けました。しかし、彼らには政治的な理由で死刑にすることは出来ません。そこでピラトのもとに連れてゆき、ローマの皇帝に叛旗を翻す人物、ローマの支配を認めない王となろうという告発がなされたのです。しかし、ピラトもナザレのイエスの姿にそのようなものを見出すことが出来ず苦慮します。罪のないこの人をなぜ殺したがるのか、憎くもないこの人になぜ自分が死刑を宣告しなければならないのか。この裁判のシーンでは、裁かれているのはイエス様ではなく、ユダヤ人とイエス様の間に立たされて板ばさみとなっているピラト自身なのです。ピラトは、この告発が一部の人々のねたみや疑いの心から出ていることを感じていました。しかし、その人々に煽動されて暴動寸前になっているイスラエルの民衆も恐ろしいものです。ユダヤの地で暴動が起こればピラト自身も失政としてマイナスの評価になってしまいます。ついにピラトは保身のため、とりあえず事態を鎮静化するため、ユダヤ人の気持ちをなだめるためと、イエス様を殺すことを認めてしまいます。決して心からではなく、心ならずも妥協してしまいます。私たちも、心ならずもイエス様を悲しませるようなことをしてしまいます。それでもイエス様は、進んで十字架を私たちのために担って下さるお方、愛の勝利と栄光を示す王なのです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*私たちの中にピラトのような姿がありませんか?
 未分類
未分類