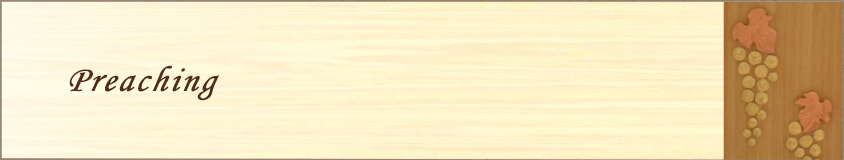「いちじくの木から教えを学びなさい」
年間主日も今日が最後となり、来週は1年の典礼暦を締めくくる王であるキリストの祭日が祝われ、翌週からはC年の待降節となり、また新しい典礼暦が始まります。今日の福音はマルコ福音書の13章が朗読されます。この13章は聖書学者たちによって「マルコの小黙示」と呼ばれることがあります。
エルサレムに入城したイエス様に最期の時が近づいています。神殿に来た弟子たちがその神殿の見事な建築を褒め称えていると、イエス様がエルサレムの将来について語りだします。イエス様の言葉はやがて、西暦70年、ローマ皇帝ティトゥスによるエルサレム陥落となって実現します。エルサレムの神殿が崩壊してしまったことは初代教会にとって二重の意味を持つことになりました。一つは、旧約の時代の完全な終わりであるということ、もう一つは、神様の臨在はエルサレムの神殿に限られるものではなく、復活したイエス様の共同体、すなわち教会にあるという確信が深められたことです。今日の朗読箇所はそれに続くもので、世の終わりの時のありさまが黙示文学的な表現で語られています。天変地異や戦乱、災害はいつの時代にも起こるものであり、そのような絶望的な災いにより終末がおとずれるのではないかと考えられることもありますが、しかし、ここで大切なのは、それが世の終わりではないこと、世の終わりとは、すなわち破壊の時ではなく、救いの完成の時であるということを理解することなのです。
イエス様ははっきりと言われています。「天地は滅びるが、わたしの言葉は決して滅びない」と。御子さえも惜しまれずこの世に遣わされた御父が、人間を滅ぼすためではなく、救うために世を完成されることへの信頼を失わないようにと、イエス様は強調されているのです。さらに、この世の完成の時がいつであるかについては父なる神様に委ねられていることなのです。
それゆえに、その終わりの時を知らない私たちはいちじくの木の教えから学ぶことが大切なのです。それは「時のしるし」を読み取ることです。世の終わり、救いの完成の時は、「今」という時間の積み重ねの中に始まっていることなのです。今という時を有意義に生きる人でなければ、その時を迎えると平静さを失ってしまうのです。「すべてに時がある」と伝道の書(新共同訳聖書「コヘレトの言葉」3章)は語っていますが、私たちに生まれてきた時があるように、私たちがこの世から離れる時も必ずやってくるのです。しかし、それは「人の子」が近づいている時であることを決して忘れてはならないのです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*あなたはどのようなことが「時のしるし」だと思いますか?
 未分類
未分類