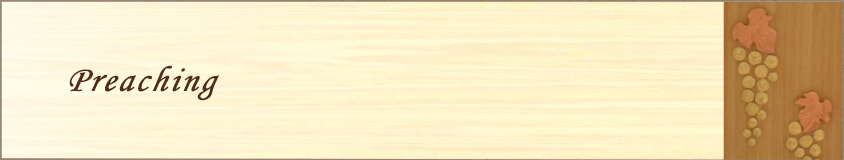「神が結び合わせて下さったもの」
十字架に向かう歩みの中で、神様が本来望んでおられることが何であるかをイエス様は明らかにされてゆきます。今日の福音書においては「離婚」の問題がファリサイ人たちから提起されました。ファリサイ人たちはモーセの定めた手続きを理由にして離婚は許されていると考えていましたが、モーセの定めた規定は「やむを得ず離別された妻がその後の生活に困窮することのないように」という配慮からのものであることを忘れて、後世の人々が「離縁状さえ渡せば離婚できる」と考えたことにそもそもの誤りがあることをイエス様は指摘します。
イエス様は律法の片言隻句よりも律法の根本精神を出発点にして発言しています。旧約時代の救いの歴史は主なる神(夫)と神の民イスラエル(妻)の出会いから婚約、結婚、そしてその破綻と再建という比喩で語られます(ホセア書)。神とその民イスラエルの関係は結婚の関係に喩えられ、それゆえ、現実の男と女の結婚の関係は神とイスラエルの間と同じく、くつがえされることのない堅固な絆として考えられているのです。
この男女の結婚の絆は、実はイエス様の十字架と復活の道にも通じるものなのです。すなわち、この結婚の絆を生きようとするならば十字架の道と同じくすべてを捧げ、犠牲を払うことなしには成り立たない道なのです。「好き」だからという理由だけでは結婚できないのです。愛するとはその人のために死ぬことだからです。人間にとって死はある意味で毎日死んでゆくことなのです。つまり、わたしたちにとって、今日この日、2024年10月6日という一日は人生においてただ1回、過ごすことが出来るだけで、繰り返すことは出来ないのです。すなわち、今日を生き、今日を死ぬのです。この人生を誰とともに過ごすのか、誰のためならばそれを捧げることが出来るのか? という問いに対する答えが「結婚」という姿、生き方なのです。だから性格も異なる男女が一緒に暮らすことは時に十字架、時に復活の栄光という両面を持つものです。
弟子たちが驚いて、「結婚しない方がましです!」と思ったほど、イエス様の教えは当時の人々にとって、鮮烈でした。そして、それは現代も同じでしょう。自分たちの人生は自分たちの勝手に考えてよいものと思っている人たちには、神様が見えていないのですから。
【祈り・わかちあいのヒント】
*「結婚は召命である」という第二バチカン公会議の教えをどう思いますか?
 未分類
未分類