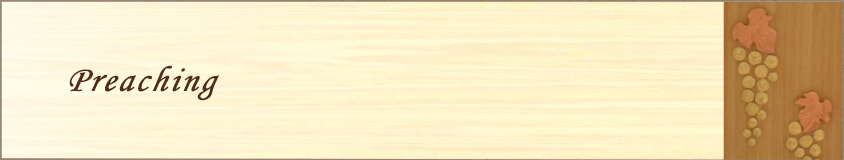「しるしを見たからではなく……」
5000人の群衆にパンを与えた大きなしるしのあと、カファルナウムでのイエス様の長い説教が始まります。しかし、このイエス様の説教は信じる人と信じない人を分けるという結末に終わるのです(年間第21主日 ヨハネ福音書6:60~69)。それはイエス様の説教の冒頭のことばに暗示されています。
「はっきり言っておく。あなたがたがわたしを捜しているのは、しるしを見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ」(ヨハネ福音書6:26)と。
しるしとは「イエス様」のことなのです。イエス様こそ、父なる神の見えるしるし、神様の愛の見える姿なのです。しかし、多くの人にとって、イエス様は「すぐれた預言者かもしれないが」、「ナザレの人で、大工の子ではないか」、「わたしたちが幼いころから知っているあの人だ」と自分たちの見ている姿にとらわれてしまい、イエス様の真の姿、真の意味を受けとめようとしていないのです。「神がお遣わしになった者を信じること、それが神の業である」とイエス様は教えておられます。このイエス様のことばは、「イエス様が神様から遣わされたお方であるということは、神様の恵みなしには理解することも信じることもできないことだ」という意味ではないか? と思います。
カファルナウムの人々はさらに「イエス様を信じるため」に条件を出します。「あなたはどんなしるしを行ってくださいますか?」、「わたしたちの先祖は荒れ野でマンナを食べました」と。このことばは「あなたが神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうか?」という荒れ野での誘惑のことばを思い出させます。条件を出し、それがかなえられたら信じてもよいという態度は信仰ではなく取り引きなのです。それは「人間が生まれてくることも神から与えられた恵みであることを忘れている」状態なのです。そして、この与えられた生命を自分のものだと考えてしまう人間が、死を迎える時、その生命が終わることに怯えるのは、「自分のものなのに取り上げられてしまう」と思っているからなのではないでしょうか? むしろ、人間として折角この世に生まれながら、人生の意味も見出せず生きることの虚しさをこそおそれるべきであり、イエス様はその意味で「決して飢え渇くことのないパン」として、わたしたち人間の心を満たす生き方を教えて下さる真の教師なのです。「イエス様は、天からのまことのパン、世に命を与えるパン」なのです。イエス様の存在とその教えなしには、「神様の愛」の意味や姿を、見ることも信じることもできないのです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*わたしたちが働くのは朽ちる食べ物のため、それとも永遠の命に至る食べ物のため?
 未分類
未分類