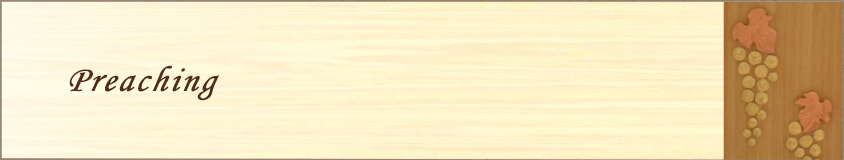今日の福音朗読では、イエス様のナザレへの訪問の記事が語られていました。マタイ福音書(13:53~58)にも同様の出来事が語られていますが、マルコ福音書はより詳しく報告しています。マルコ福音書を注意深く読んでみると、このナザレへの訪問はイエス様の宣教活動の転換点になっています。
宣教活動の初期、イエス様は弟子たちとともにガリラヤ中をめぐり歩き、方々の会堂で教えを述べておられました。しかし、このナザレの会堂を最後にして、それ以後は「会堂」で教えを述べることをなさいません。つまり、イエス様はナザレの会堂における人々の「驚くべき不信仰」を体験されてからは、二度と「会堂」には足を踏み入れないのです。マタイ福音書とマルコ福音書は「会堂」(=教えの固定化のシンボル)を全ユダヤ人の不信仰の典型とみなしていたのでしょう。
ナザレの人々がイエス様をすなおに受け入れることができなかったのは何故でしょう? 彼らは「大工ではないか? マリアの息子ではないか? その兄弟(当時はいとこのような近い親族も兄弟姉妹と呼んでいました)を知っている、一緒に住んでいるではないか?」と口々に叫んでいます。つまり、「これまで知っていたイエスの姿」にこだわるがゆえに「眼の前にいるイエス様」を受け入れられないのです。イギリスの哲学者フランシス・ベーコンは、人間が陥りがちな偏見を「イドラ」と呼んで警戒するように述べていますが、ナザレの人々はまさに「会堂のイドラ」にとらわれていたのでしょう。つまり、人の子としてのイエス様のことを幼いころから知っていると思い込んでいたからこそ、神の子としてのイエス様の姿を受け入れられなかったのでしょう。マタイとマルコがこのエピソードを重要視しているのは、私たちにとっても大切な意味があるからです。私たち自身にも「ナザレの人々と同じ不信仰」が潜んでいるからです。私たちは「聖書について、教会の教えについて、この教会のことについて」知っていると思うほど、イエス様が今日、ここで、私たちになさろうとしていることを受け入れなくなるのです。聖書には「今日、み声を聴くこと」の大切さが繰り返し述べられているのです。
福音書の中で、「イエス様が驚かれた」というエピソードが二つあります。一つは今日の箇所で「故郷ナザレの人々の不信仰に驚かれた」ということ、もう一つは「異邦人である百人隊長の信仰に驚かれた」(ルカ7:1~10)ことです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*私たちは、どちらの意味でイエス様を驚かせるでしょうか?
私たちの信仰、それとも不信仰?
 未分類
未分類