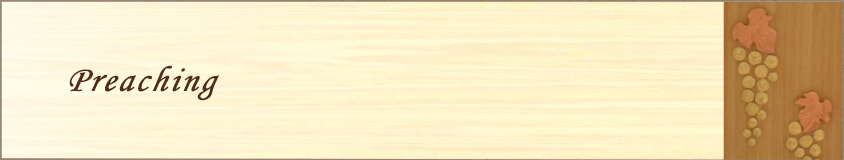「神の国を何にたとえようか」
今週から年間主日の典礼季節となりました。今年はB年ですので、年間主日の福音はマルコ福音書が継続的に朗読されます。今日の福音朗読はマルコの4章からです。マルコ福音書の1章21~45節には第1の奇跡物語が収録されています。来週の年間第12主日から第14主日までは、マルコ4章35節から6章6節までの第2の奇跡物語がまとめて読まれます。この第2の奇跡物語は物語風の描写が豊富で、イエス様だけでなく多くの人物が登場します。弟子たち・会堂長ヤイロ・長患いの女性などで、その中心的なテーマはイエス様と出会い、交わりをもつ人々の「信仰」です。
このマルコ福音書の第2の奇跡物語の直前におかれているのが、今日の福音朗読箇所なのです。この小さなたとえ話はマルコ福音書にのみ登場するもので、「成長のたとえ」と呼ばれることがあります。「春来草自生」(春来たらば、草おのずから生ず)という禅語がありますが「一心につとめていれば、しかるべき時に、自然と草木は芽を出すもの、焦りは禁物、じっとその時を待つ泰然自若の心こそ大事」という意味があるのです。イエス様の成長する種のたとえもまた、神様のタイミングというものの大切さを教えているのではないでしょうか? 時々、私たちは焦ってしまいます。「神様、神様、私たちがこんなに困って、こんなにお祈りしているのに、何故何もお答え下さらないのですか?」という思いにとらわれたりしてしまいます。しかし、神様の方からすれば、「こんなにこれまで、多くのことを与えて来たのにどうしてそれを生かさなかったのか?」と神様をやきもきさせていたのかも知れません。神様の時は「永遠の今」、すなわち遅すぎることも早すぎることもない、神様だけがなしうる絶妙の時、タイミングがあると信じることが大切なのです。
もう一つのたとえはからし種のたとえです。「地上のどんな種よりも小さい」といわれる種が、やがて「空の鳥が巣をかけるほど大きな枝をはる」ように成長してゆくのです。神様が私たちの心に蒔こうとされているものは目立たぬ小さなものですが、それは成長してゆくものなのです。その種を枯らしたり、空の鳥に奪われたり、茨や雑草で覆ってしまわない限り、私たちの心にどっしりとした根を張るのです。わずかなきっかけ、小さな出会いが、やがてイエス様を通して、父なる神の大きな愛につながってゆくのです。このたとえ話のあとに登場する様々な人々は、病気をはじめとする苦しみの中にあって、イエス様と出会いました。そしてそれぞれの人は、その人の持つ信仰によって、「奇跡」に出会うのです。
【祈り・わかちあいのヒント】
*私たちの心に蒔かれた小さな種とはどんなことでしょう?
*イエス様に出会えたことは小さな奇跡では……?
 未分類
未分類